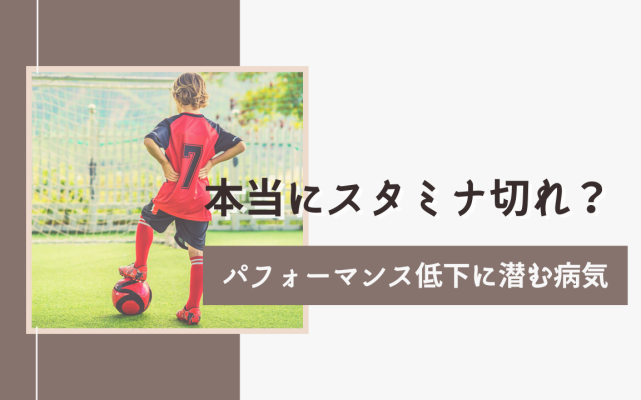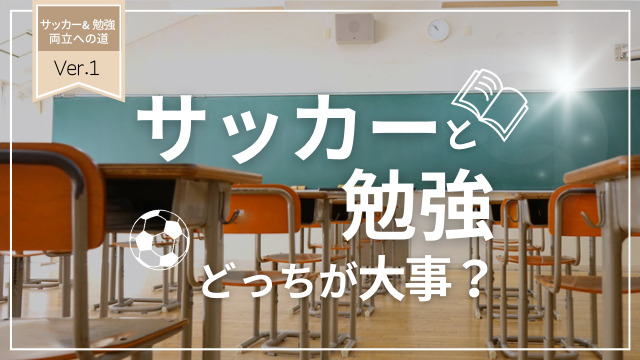「走れない…すぐにバテる」 と言っていたら、まず考えるのはスタミナ切れではないでしょうか? 「体力が足りないんだよ!毎日走って体力をつけよう!」 という発想になることが多いと思います。 もちろん、普通の状態なら走って体力をつけることは大切ですし、効果のある方法だと思います。 でも、あくまで 『普通の状態なら』…。 うちの息子が試合で走れないと言い出した時には、私も「体力不足だろうな」と思っていました。 でも、トレーニングはしているはずなのにな?足りないのかな?という疑問が。 すると、体力不足以外の問題が浮上してきたのです。 「子供がサッカーで走れない・走らない」のではなくて、もしかしたら「走れない」のかもしれません。 今回は、走れなくなる原因をまとめてみました。
サッカーをする子供に隠れている可能性のある病気
走れなくなる裏には、病気が隠れている可能性があります。 「でも、うちの子元気だし。学校の健康診断でも一度も引っかかったことがないよ。」 そうなんです。一見、元気なんですよね。 日常生活や学校の体育くらいでは問題ないことがほとんどです。 だからこそ厄介で、病気を疑うことはなく見逃されてしまうのですが…。 「走れない」と感じたら、以下の病気のような症状がないかも確認してあげてください。
運動誘発性喘息
日常生活では全く問題ないのですが、運動をすると気管支が締まって息が吸いにくくなる(喘息症状)が出るのが特徴です。 「喘息ならさすがに気付くでしょ?」 と思うのですが、この喘息、普段の生活では全く症状がでない事も多いので、とにかく気付きにくいです。 呼吸機能検査でわかります。 走ると苦しい 普段は平気だが、運動すると身体が重い 集中できない などの症状が出るようです。 うちの息子が走れなくなった理由はズバリこれだったのですが、自覚症状は「走れなくなった」のみ。 きっと体が重かったり息苦しかったりもしたのだと思いますが、語彙力のない息子はここまで伝えてきませんでした…。 一緒にサッカーをしていると「ヒューヒュー」喘息音のような音がするのですが、相当気をつけて聞かないとわかりませんし、ご自身が喘息持ちなど喘息の症状を知っている方でないと周囲からは気付くことが難しいと思います。 なので、個人的には違和感を感じたらとりあえず病院! が安心だと思っています。 治療は、通常の喘息と同じように吸収薬を使います。 運動前に吸入して、アップをしっかりしておけば一試合は走り切ることができるそうです。 ただ、1日に何試合もあったりすることが多い場合には、朝晩1日2回使う吸入ステロイド薬に変えた方がいいこともあります。 病院で状況を詳しく話すことで一番良い方法を考えてくれますので、できるだけ練習や試合のスケジュール感も話した方がいいですね。 気になることはどんどん質問していくのがいいと思います。
スポーツ性貧血
うちの子は貧血は大丈夫でしたが、周囲では結構聞く話です。 スポーツで足の踵に衝撃を受けることで、赤血球が壊れてしまい貧血になってしまう病気です。 貧血なので、血液検査をすればわかります。 たかが貧血と軽視されがちですが、 身体が重い 集中できない(ぼーっとする) 息切れ 爪やまぶたの裏が白っぽい などの症状が出るようです。 サッカーをやっている子は体力のある子が多いため、貧血でも普段の生活は全く問題なく過ごせてしまう子も多いです。 ただ、サッカーをやっているといつもと違う違和感を感じて、原因がわからずモヤモヤを抱えている状態になりがちです。 サッカーをしている子は、運動していない子よりも多くの鉄を必要としています。 そのため、運動していない子では通常値となる血液検査の結果でも、サッカーをしている子にとっては貧血という状況もあり得ます。 何かで血液検査をした時には問題なくても、スポーツ内科の観点から見れば貧血。 これは見逃されてしまいますよね。 やっている競技によっても基準値が違ってくるそうなので、専門医に相談するのが安心だと思います。
何科を受診すればいいの?
気になる症状があったら病院を受診して検査をしてもらうのが安心です。 喘息や貧血は小児科や内科、呼吸器科で診てもらえますが、運動がきっかけになっている病気ですし、今後も安心してスポーツを続けていけるかどうか診てもらうという意味では『スポーツ内科』を受診するのがオススメです。 『スポーツ内科』というのは聞きなれない言葉ですが、最近徐々に増えており、文字通りスポーツに視点をおいて診療をしてくれたり、各スポーツの特徴を考えた上で、日常生活だけでなく競技を続けて行くための提案をしてくれます。 まだまだ数は少ないですが、探すと結構あります。 インターネットで「スポーツ内科 (お住まい地域)」で検索すると、情報が得られますので、ぜひ探してみてください。 スポーツ内科は、初診時の問診に30分くらいかかることが多いです。 そのため、予約制になっている病院もあるので、まずは病院に問い合わせてみてください。 もし、お近くにスポーツ内科がない場合には、近所の小児科や内科で事情を話し、念の為検査を受けたい旨を伝えれば検査ができる病院を紹介してくれるはずです。 気になる症状がある場合は、一度検査を受けてみると安心できると思います。 少し話はズレますが、捻挫などをしたら整形外科を受診されるかと思いますが、この時にもスポーツ整形外科を専門にされている医師がいる病院に行くのがオススメです。 リハビリも競技に合わせた提案をしてくれます。 日常生活とスポーツ時って大きく違います。 スポーツをやっている子とやっていない子では体のつくりも違っています。 やはり専門医に診てもらうのが安心できると思います。
まとめ
選手本人も自分の体の変化に気づいていなくて、プレーの質が落ちて辛い想いを募らせていることも少なくありません。 スタミナを付けようとトレーニングを重ね、症状が悪化してしまうこともあります。 (うちの息子がこのパターンでした。) でも、問題は別のところにあるのですから、トレーニングをしても解決しっこないんです。 選手本人は身体がツラいのはもちろんのこと、精神的に負担が何よりツラいと思います。 何をしても解決しない。 もうサッカーができないのではないか。 自分の限界なのではないか。 口に出さなくても、気持ちが追い込まれていることもあります。 原因がわかれば薬でコントロールできますので、今まで通りに走れるようになりますし、サッカーが安心して続けられます。 『今までよりも走れなくなった』と感じたら、病院を受診してみることも大切だと思います。 ただ、走れない原因が『疲労』にあることも… 「試合スケジュールが詰まっていて疲労が抜けないのを実感している」 など、原因が疲労にありそうな場合ですよね。 今回ご紹介した症状の中で「これ!」という症状に当てはまらなければ、疲労回復のためにまずはサプリメントで様子をみるのもいいのかもしれません。 もし、一ヶ月くらいしても全く変わらなければ、やはり一度病院に行ってみることをおすすめします。 わが家で3年愛飲している疲労回復サプリメントです。 ↓↓↓ アスリートのためのアミノサプリメントはこちら(体験談です) これでダメなら病院!とわが家の基準となっています。笑